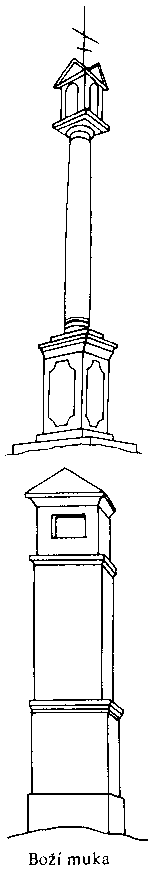 一九一六年に、画家でもあった兄のヨゼフ・チャペックとの合作『輝く深淵とその他の散文』を最初の単行本として出版したカレル・チャペックは、翌一七年に、最初の単独の作品『受難像』を上梓し、これによって改めて単独の作家としてデビューした。『受難像』は、チャペックの独立した文学の道の最初に位置する作品であり、多くの点で、後の彼の諸作品を予示している。
一九一六年に、画家でもあった兄のヨゼフ・チャペックとの合作『輝く深淵とその他の散文』を最初の単行本として出版したカレル・チャペックは、翌一七年に、最初の単独の作品『受難像』を上梓し、これによって改めて単独の作家としてデビューした。『受難像』は、チャペックの独立した文学の道の最初に位置する作品であり、多くの点で、後の彼の諸作品を予示している。
 チャペック小説選集第1巻
チャペック小説選集第1巻
K・チャペック著/石川達夫訳
四六判上製/200頁/定価2039円(本体1942円+税)
人間が出会う、謎めいた現実。その前に立たされた人間の当惑、真実を探りつつもつかめない人間の苦悩を描いた13編の哲学的・幻想的短編集。真実とは何か、人間はいかにして真実に至りうるかというテーマを追求した、実験的な傑作。(1995.10)
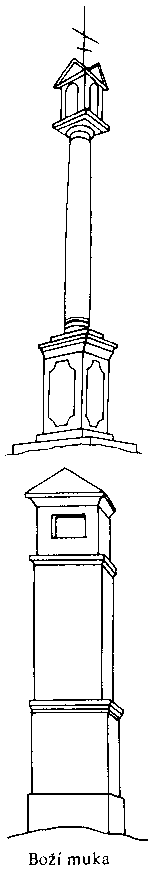 一九一六年に、画家でもあった兄のヨゼフ・チャペックとの合作『輝く深淵とその他の散文』を最初の単行本として出版したカレル・チャペックは、翌一七年に、最初の単独の作品『受難像』を上梓し、これによって改めて単独の作家としてデビューした。『受難像』は、チャペックの独立した文学の道の最初に位置する作品であり、多くの点で、後の彼の諸作品を予示している。
一九一六年に、画家でもあった兄のヨゼフ・チャペックとの合作『輝く深淵とその他の散文』を最初の単行本として出版したカレル・チャペックは、翌一七年に、最初の単独の作品『受難像』を上梓し、これによって改めて単独の作家としてデビューした。『受難像』は、チャペックの独立した文学の道の最初に位置する作品であり、多くの点で、後の彼の諸作品を予示している。
『受難像』は、原題ではボジー・ムカと言い、文字通りには「神の苦しみ」という意味である。ボジー・ムカとは、石か煉瓦の柱の上部に厨子のような角柱の箱をつけ、その中に十字架に架けられたキリストや聖者の像を安置したもののことで、よく田舎の十字路に置かれている。この『受難像』という題名について、チャペック自身があるインタヴューの中で、「『受難像』という題名は二重の意味を持っており、一つは岐路を意味し、もう一つは至高の事物とその探求による自虐を意味します」と述べている。岐路に立たされた人間の苦悩と期待、踏み慣れた日常的な道からの離脱と今まで見えなかった真実の瞥見、隠れた真実や神秘的・奇跡的なものの探求、その探求の困難さと苦しみ――これらが『受難像』という題名に込められていると考えてよいであろう。
『受難像』は、十三編の短編から成る短編集である(いうまでもなく、十三は、題名とも関連する特別な数である)。この短編集に収められた個々の作品の執筆時期は、一九一三年から一七年にわたるが、そのほとんどは一六〜一七年に書かれている。つまり、一九一四年から一八年まで続いた第一次世界大戦のさなかに書かれたものであり、この大規模な戦争が『受難像』に影を落としていることは疑いない。また、チャペック自身の苦しい私生活も反映している。一九一五年にカレル大学で哲学博士号を取得して勉学を終えたチャペックは、脊椎の病気と、ままならない職探しのために、不安定な生活を強いられていた。しかも、彼の病気は当初、死病と誤診されていた。彼はようやく一九一七年十月に『ナーロドニー・リスティ(国民新聞)』に就職して生活の安定を得るが、それまでの、大戦と困難な私生活の、いわば二重の実存的不安の時代に、これらの諸短編が書かれたわけである(チャペックが、後の軽妙な諸作品からは想像しにくい、このような苦悩の中から出発しているということは、記憶しておくべきであろう)。
戦争と死病に由来する死の不安は、チャペックの意識を死と対峙させ、日常的・習慣的なものから引き離し、人生や世界を見つめる目を研ぎ澄まして、いわば末期の目とした――あるいは、『受難像』という題名の意味に即して言えば、岐路に立たされた人間の目とした――ことであろう。死の不安はまた、彼の中に奇跡への渇望をも生み出したと思われる。この個人的な奇跡の期待は、同時に、三〇〇年間独立を奪われていたチェコ民族が、大戦という死の危険を通して奇跡的に解放されるのではないかという、民族的レベルでの奇跡の期待とも結びついていた。チャペックは、一九二八年に、ある手紙の中で次のように書いている。「『受難像』の本来のモチーフは、一つは戦争(そしてまた、我々チェコ人にとって戦争が良い結末をもたらすという奇跡の期待)であり、もう一つは――誤診に基づいていたのですが――死病と、それゆえに人生の決算とでもいうものです」。また、一九一七年には、やはり手紙の中で次のように書いている。「『受難像』という題名は、岐路ないし人生の十字路を意味します。[……]これは、反主知主義的な本であり、あらゆる合理的なものの危機と崩壊の本です。その鍵は、例えば『悲歌』であり、それから『山』です。人間は、岐路で――自分の合理的・習慣的な生活、理性と内的安楽のメカニズムが終わる地点で――何かの内的ないし外的な出来事に出会います。どの道を行ったらよいのか分からないときのように、未知のもの、謎めいたものに出会います。それは、恐ろしい不安と不確かさ、痛み、悲しみ、模索の感覚です。足の下の大地を失い、為すすべを知らずに立ち尽くすのです。そして、そこで、彼の中に魂の声が、最初の、ほとんど子供のような方向づけが、響きます。謎の解決では決してなく、単に自分の内側への転換、内面化です」。『受難像』に満ちている、日常的なものと非日常的なものとの対峙、不安と期待の雰囲気、謎めいたものと内面的な未知の探究、岐路に立たされた人間の心情などは、多分に、民族的・世界的・歴史的事件とチャペック自身の私生活とが重なり合った所から出てきたものである。
このような、『受難像』が書かれた時代の状況とも関連するが、『受難像』には表現主義的な傾向が多分に認められる。近代的世界観の動揺は、とりわけ第一次世界大戦によって決定的となり、人々は既存の世界観・人生観・価値観に安住できなくなった。古い世界が崩壊してゆくが、新たな世界はいまだ訪れない。表現主義の文学は、このような状況の中から生まれた存在の不安と痛みの文学であると言われるが、このような性格は、『受難像』にもはっきりと認められる(そもそも、『受難像』という題名が、きわめて表現主義的だと言えよう)。内面的・主観的な感情表現の重視、文章構成の放漫化と語の累積凝集といった表現主義の文体的特徴も、『受難像』には認められる(例えば「時の膠着」や「誘惑」)。
表現主義と並んで、『受難像』には、対象を異なる視点から見た構成要素に分解した上でそれを再構成するキュービズムの傾向も、多分に認められる。キュービズムは、チェコでは豊かな伝統を形成し、プラハはパリに次いでキュービズムの最も重要な中心地と見なされるほどで(ちなみに、プラハには、ヨーロッパでも珍しいキュービズム建築が残っている)、初めカレルと合作していた兄のヨゼフも、キュービズム的な芸術家集団「オスマ」に属し、キュービズム絵画を描いている。『受難像』においては、現実はレアリズム小説のように「神の視点」から見た全体的・統一的な形では示されず、限定された相対的視点から見た現実の断片が提示されて、それらの断片(の集まり)から現実を再構成しようとする形で、人間と現実との係わりが示されている。
『受難像』は、チャペックの作品の中でも最も実験的・前衛的なものと言えるだろう。チャペックは『受難像』以後、前衛的な方向には進まず、むしろアヴァンギャルド的芸術家たち(例えば、両大戦間チェコのアヴァンギャルド芸術運動の主要な担い手となった芸術家集団「デヴィエトスィル」)に対立するようになるのだが、それでも、チャペックのキュービズム的な現実把握法は、真実とは何かを追究して人間にとっての現実の意味を探ろうとする哲学的志向と、現実の謎を解明しようとする推理小説的手法と重なる形で残ることになる(特に、『ホルドゥバル』『流れ星』『平凡な人生』という三部作において)。もっとも、推理小説的手法は、チャペックにおいて、真実の捉え難さという哲学的テーマの支配のもとで意図的に歪められており、『受難像』の中の「足跡」や「山」におけるように、推理小説的な状況とサスペンスはあるが、解決はなく、(推理的方法によっては)最終的真実は解明されない(このことは、後の『ホルドゥバル』においても同様である)。「山」においては、芸術家イェヴィーシェクの直感がおそらく最も真実に近いところに至るが、このような直感の重視は、チャペックが直感を重んじたベルグソンの哲学などから影響を受けたこととも関係があると考えられる。
ところで、十九世紀的なレアリズムは、作品の中で語られる出来事を客観的に記述して、読者に事実を直接見たように提示しようとし、現実の直接的な知覚と真実性の印象を生み出そうとした。このような傾向に対して、レアリズムの克服の時代には、出来事についての報告を出来事自体から区別し、事実の提示の仕方に注意を向ける傾向、また、出来事を現実的な時間の流れたる単純な時間的連鎖から解放しようとする傾向が、現れた。チェコの美学者ムカジョフスキーが指摘しているように、チャペックの『受難像』は、まさにこのような傾向を現しており、とりわけ「足跡」は典型的である。新雪の野にたった一つだけついた足跡は、我々が慣れている事象の通常の連関を破壊するものであり、謎である。しかしながら、この謎は小説の中で結局解決されず、どうしてこのような足跡がついたのかという、語りの本来の対象となるべき出来事は隠れたままに残る。それによって、事実としての出来事と、それについての報告としての語りとの間に、はっきりとした隔たりが生じ、事実自体はむしろ背景に退いて、事実の様々な可能性と解釈と語りが、前面に出てくる(このことは、身元不明の瀕死の男の人生を三人の人間が推理して様々な展開をもつ物語とする、後の『流れ星』において顕著となる)。「無言の話」においては、一人の男の人生の物語という、本来の語りの対象としての事実のうち、読者に提示されるのは、ほとんど「**ERTA *EL SOL」という消えかけた文字だけであり、ただその事実をめぐる架空の報告が試みられ、語りの印象が作られる。「助けて!」においては、助けを求める叫びに関する出来事はついに明らかにされず、小説の主要事となるのは、その叫びに触発された主人公の内面の動きである。『受難像』に収められた作品の多くにおいて、事件の最も本質的な部分は「舞台裏」に追いやられており、事件のうち我々に与えられるのは、いわば氷山の一角にすぎず、大部分は水面下に隠れているのである。「銘」の主人公は、「元へ」という一つの言葉をきっかけに、いわば水面下に没している厖大な自分の過去を思い出し、再認識しようと試みる。我々は、自分自身の過去でさえ、その大部分は、水面下の氷山のように、はっきりと見えず、認識せず、十分に経験してさえいないのである。自分自身の過去が既知のもののように思えるのは「無邪気な誤り」だという主人公の言葉は、おそらく我々の現実認識一般に当てはまる。我々が無邪気にも分かったような気になっている人生と世界の様々な事象は、実際には謎に満ち満ちているのである。「足跡」のボウラが言うように、我々が「一定の規則に慣れてしまっているために、それに出会っても何も思いつかない」ような謎がたくさんあるのである。
『受難像』の中の幾つかの短編は、推理小説的形式をもった哲学的小説であり、『受難像』は、「真実とは何か?」「人間はいかにして真実に至りうるか?」という、チャペック生涯のテーマを扱った最初の作品と言える(このテーマは、後に『ホルドゥバル』『流れ星』『平凡な人生』という三部作において全面的に展開されることになる)。また、キュービズム的傾向とも関係することであるが、チャペックは既に『受難像』において、観点の多様性と現実認識の多様性、人間の人格の多様性、人間生活の多重の潜在的可能性という、後に三部作で大きく扱われるモチーフを展開している。
しかしながら、『受難像』の諸短編は多分に哲学的なものであるとはいえ、文学的なイメージの造形や特定の気分の文学的表現という性格を強く持つことはもちろんである(とりわけ第二部に収められた諸短編)。チャペック自身、ある手紙の中で、『受難像』のすべての短編は思想としてではなくて体験として始まったのであり、「足跡」は雪、「悲歌」は酩酊、「山」は速さと遅さ、「消えた道」は夜、「幻像」は水、「無言の話」は晴れた日の体験であり、登場人物はこれらの印象の凝縮にすぎない、と述べている。そして、「思想は、もともと何かの探究に奉仕するものではなくて、それによって私が一定の自然の印象を表現したかった、気分的・叙情的な要素」であり、「状況と思想は同じ一つの全体」であると述べている。我々は、『受難像』の諸短編を哲学的に読むばかりでなく、例えば、新雪の野原につけられたたった一つの足跡という鮮烈なイメージや印象を味わうことができるのである。
なお、翻訳にあたっては、一九八一年に出版された、チェコスロヴァキア作家同盟版の『カレル・チャペック作品集』第一巻を底本とした。