幸福のおすそ分け
文中で、色が付いた言葉をクリックすると、その説明を読むことができます。そして、いよいよ、貴重な音声(!!)が聴けます。
アルムステル大佐は一九四四年七月二十日、ヒトラーにたいする暗殺未遂のあと、ベルリンのモアビト監獄に投獄された。有罪の決定的証拠が見つかった将軍たちは、みな処刑された。アルムステル大佐と他の何人かは、証拠がなかったので極刑をまぬがれた。赤軍が一九四五年五月にベルリンを解放したとき、彼が生きていたのはそういう理由からだった。
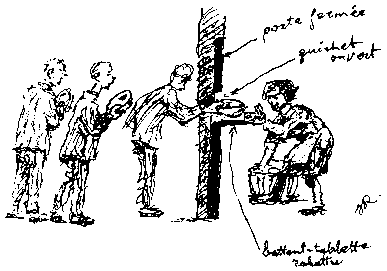 それからどうなったか私は知らない。一九五五年五月、東シベリアのアレクサンドロフスク監獄の監房で、私は昼の水っぽいスープをもらうために飯盒を持って並んでいるアルムステル大佐のすぐ後にいる。他のすべてと同様、大佐は痩せて、丸刈りにし、縞のパジャマを着ている。われわれ三十人ほどは、まだ閉まっている扉の前で待っている。差し入れ口だけが開いている。その開口部の板は監房の外側に水平に倒れて、そこに飯盒を置くことができる。廊下の給食係の女は、きれいかどうか疑わしい手袋をはめた左手で飯盒をとると、右手に持っているお玉で手桶の中身を力強くかきまわしてから、飯盒のなかに配給のスープを注いで、それを開口部の上に置く。相手はそれを指が火傷しないように両手でうやうやしく受け取る。なぜなら飯盒はアルミ製だからだ。それからしゃつちょこばった格好でそこからたち去る。給食婦はゆうに三十歳を超している。美人でないし、化粧もしていない。表情に意地のわるいところは少しもない。彼女はただ白分の仕事をしているだけである。われわれは彼女がわざわざ桶の中身をよくかきまわしてくれることに感謝している。なぜならスープはとても水っぽくて、魚のスープなら骨片だとか肉のスーブなら筋や靭帯といった固形物は、すべて底にあるかも知れないからである。われわれの給食婦はNKVDの兵長だが、けっしてこれ見よがしに軍服を着ていることがない。彼女は素朴なロシアの農婦のような服を着ている。彼女の上官はこの規律違反を大目に見ている――なにしろここはモスクワから七千キロも離れたところだ。われわれは内輸だけで、愛情をこめて彼女を「マーシャ*」と呼んでいる。
それからどうなったか私は知らない。一九五五年五月、東シベリアのアレクサンドロフスク監獄の監房で、私は昼の水っぽいスープをもらうために飯盒を持って並んでいるアルムステル大佐のすぐ後にいる。他のすべてと同様、大佐は痩せて、丸刈りにし、縞のパジャマを着ている。われわれ三十人ほどは、まだ閉まっている扉の前で待っている。差し入れ口だけが開いている。その開口部の板は監房の外側に水平に倒れて、そこに飯盒を置くことができる。廊下の給食係の女は、きれいかどうか疑わしい手袋をはめた左手で飯盒をとると、右手に持っているお玉で手桶の中身を力強くかきまわしてから、飯盒のなかに配給のスープを注いで、それを開口部の上に置く。相手はそれを指が火傷しないように両手でうやうやしく受け取る。なぜなら飯盒はアルミ製だからだ。それからしゃつちょこばった格好でそこからたち去る。給食婦はゆうに三十歳を超している。美人でないし、化粧もしていない。表情に意地のわるいところは少しもない。彼女はただ白分の仕事をしているだけである。われわれは彼女がわざわざ桶の中身をよくかきまわしてくれることに感謝している。なぜならスープはとても水っぽくて、魚のスープなら骨片だとか肉のスーブなら筋や靭帯といった固形物は、すべて底にあるかも知れないからである。われわれの給食婦はNKVDの兵長だが、けっしてこれ見よがしに軍服を着ていることがない。彼女は素朴なロシアの農婦のような服を着ている。彼女の上官はこの規律違反を大目に見ている――なにしろここはモスクワから七千キロも離れたところだ。われわれは内輸だけで、愛情をこめて彼女を「マーシャ*」と呼んでいる。
マーシャの動きは正確で早い。差し入れ口の行列は早く進む。まもなくアルムステル大佐の番だ。われわれは有名なベルリンの人類学博物館の宝についてのフランス語の会話を中断する。大佐はマーシャに飯盒を差し出して、かがんで、ごく丁寧に言う。「カルトーフェル〔馬鈴薯〕!」
ソ連の監獄に十二年間閉じ込められている彼は、いまなおプーシキンやレーニンの言葉は話さない。しかし、「馬鈴薯」のように、ロシア語とドイツ語が同じ「カルトーフェル**」というような言葉がある。私は大佐の肩越しにマーシャのひとのいい微笑を見逃さない。彼女はすいませんというふうに不可能だという身振りをしたのだ(規則では命令を与えるとき以外、囚人に個人的に話し掛けることは禁止されている)。
飯盒を持ってたち去るまえに、大佐は私をふりかえる。喜びにあふれ、ほとんど勝ち誇った表情で言う。「もしあったら、彼女はわしにくれただろう!」
私は彼が幸福のおすそ分けをしてくれたことに感動する。
*マーシャはマリーヤの愛称。
**ロシア語は「カルトーフェリ」でドイツ語から来ている。
HOME|
既刊書|
新刊・近刊書|
書評・紹介|
チャペック|
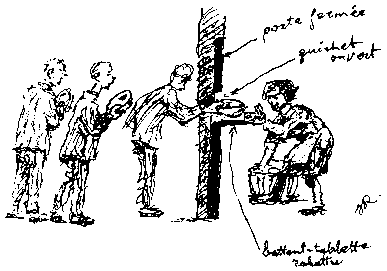 それからどうなったか私は知らない。一九五五年五月、東シベリアのアレクサンドロフスク監獄の監房で、私は昼の水っぽいスープをもらうために飯盒を持って並んでいるアルムステル大佐のすぐ後にいる。他のすべてと同様、大佐は痩せて、丸刈りにし、縞のパジャマを着ている。われわれ三十人ほどは、まだ閉まっている扉の前で待っている。差し入れ口だけが開いている。その開口部の板は監房の外側に水平に倒れて、そこに飯盒を置くことができる。廊下の給食係の女は、きれいかどうか疑わしい手袋をはめた左手で飯盒をとると、右手に持っているお玉で手桶の中身を力強くかきまわしてから、飯盒のなかに配給のスープを注いで、それを開口部の上に置く。相手はそれを指が火傷しないように両手でうやうやしく受け取る。なぜなら飯盒はアルミ製だからだ。それからしゃつちょこばった格好でそこからたち去る。給食婦はゆうに三十歳を超している。美人でないし、化粧もしていない。表情に意地のわるいところは少しもない。彼女はただ白分の仕事をしているだけである。われわれは彼女がわざわざ桶の中身をよくかきまわしてくれることに感謝している。なぜならスープはとても水っぽくて、魚のスープなら骨片だとか肉のスーブなら筋や靭帯といった固形物は、すべて底にあるかも知れないからである。われわれの給食婦はNKVDの兵長だが、けっしてこれ見よがしに軍服を着ていることがない。彼女は素朴なロシアの農婦のような服を着ている。彼女の上官はこの規律違反を大目に見ている――なにしろここはモスクワから七千キロも離れたところだ。われわれは内輸だけで、愛情をこめて彼女を「マーシャ*」と呼んでいる。
それからどうなったか私は知らない。一九五五年五月、東シベリアのアレクサンドロフスク監獄の監房で、私は昼の水っぽいスープをもらうために飯盒を持って並んでいるアルムステル大佐のすぐ後にいる。他のすべてと同様、大佐は痩せて、丸刈りにし、縞のパジャマを着ている。われわれ三十人ほどは、まだ閉まっている扉の前で待っている。差し入れ口だけが開いている。その開口部の板は監房の外側に水平に倒れて、そこに飯盒を置くことができる。廊下の給食係の女は、きれいかどうか疑わしい手袋をはめた左手で飯盒をとると、右手に持っているお玉で手桶の中身を力強くかきまわしてから、飯盒のなかに配給のスープを注いで、それを開口部の上に置く。相手はそれを指が火傷しないように両手でうやうやしく受け取る。なぜなら飯盒はアルミ製だからだ。それからしゃつちょこばった格好でそこからたち去る。給食婦はゆうに三十歳を超している。美人でないし、化粧もしていない。表情に意地のわるいところは少しもない。彼女はただ白分の仕事をしているだけである。われわれは彼女がわざわざ桶の中身をよくかきまわしてくれることに感謝している。なぜならスープはとても水っぽくて、魚のスープなら骨片だとか肉のスーブなら筋や靭帯といった固形物は、すべて底にあるかも知れないからである。われわれの給食婦はNKVDの兵長だが、けっしてこれ見よがしに軍服を着ていることがない。彼女は素朴なロシアの農婦のような服を着ている。彼女の上官はこの規律違反を大目に見ている――なにしろここはモスクワから七千キロも離れたところだ。われわれは内輸だけで、愛情をこめて彼女を「マーシャ*」と呼んでいる。