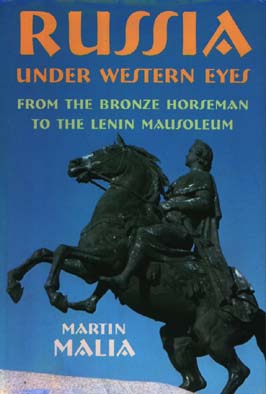
「マーティン・メイリア」の名前は、主として"Alexander Herzen and the Birth of Russian Socialism(ゲルツェンとロシア社会主義の誕生)"(1961年)の著者としてつとに知られていた。これはゲルツェン研究の書としてばかりか、近代ロシア思想史研究の書としても、すでに古典としての地位を得るに至っている名著である。最近はこれに大著"The Soviet Tragedy: A History of Socialism in Russia,1917-1991"(1994)が加わることにより、彼の文名は思想史研究者の範囲を越え、更にはロシア学者の範囲をも越え、現代史に関心を持つ多くの人々の中に広く行き渡るに至ったという感がある。この本には白須英子氏による優れた翻訳があるので、わが国でもその名を知る人の数はすでに少なくないはずだ。(『ソヴィエトの悲劇――ロシアにおける社会主義1917-1991』上・下、草思社、1997年、以下では『悲劇』と略称する)
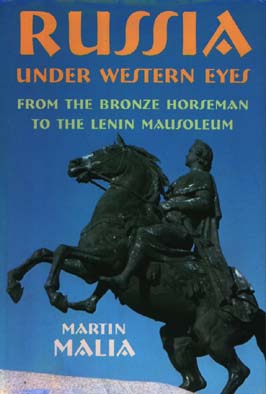 |
先ず、本書の目次を示すことから始めよう。
「序 謎のロシア
1 啓蒙的デスポチズムとしてロシア 1700-1815年
2 オリエンタル・デスポチズムとしてのロシア 1815-1855年
3 戻ってきたヨーロッパとしてのロシア 1855-1914年
4 戦争と革命 1914-1917年
5 ソヴィエト・ロシアの姿見を通して 西欧はそこに何を見たか 1917-1991年
結論」
この度の著作がその内容からして『悲劇』と重複するところが少なくないのは当然のことだろう。例えば、『悲劇』の「はじめに――歴史的手問題点、審判の時」と第1部「社会主義の起源」(邦訳では上巻13-147ページ)が『西欧の眼』の「序」から「4」(原著1-231pp.)までに書かれていることの骨子であり、逆に、『眼』の「5」(原著89-407pp.)は『悲劇』の残りの部分(第2部-第4部章、邦訳上巻151-427ページ、下巻11-322ページ)の骨子となっており、そして、『悲劇』の「エピローグ」(邦訳下巻323-345ページ)と『眼』の「結論」(原著409-435pp.)は互いにほぼ対応し合う、といった具合である。
前著『悲劇』が衝撃的であった所以は、大胆にも、ソビエト体制全体をマルクス・レーニン主義なるイデオロギーに支配された巨大な虚妄であったとする命題を、ソ連邦の政治・経済に関する該博な知識、なかんずく豊富な思想史の知識を駆使して、論証しようとしたことにあるが、この度の大著『西欧の眼』はソヴィエトのこのイデオロギーの仕掛けを西欧は何故見抜けなかったのかを、近代西欧とロシアの関係の始まりに逆上り、しかも主として西欧側の事情に内在して、明らかにしようとしたものである。その意味で二つの著作は「合わせ鏡」のような関係にあることが分かる。
西欧にとってロシアは久しく「謎」の国と呼ばれてきた。しかし、メイリアによればそのようなイメージはつまるところ自分たちの利害関心の投影に過ぎず、しかも自分たちの概念をロシアにあてはめることによって生じた幻影にほかならない、という。
例えば「西欧対ロシア」という対立の図式――これは実際には1830年代、ニコライ一世の時代に西欧において形成された観念である。それまでのロシア、とりわけピョートル一世から女帝エカテリナに時代、ロシアの専制体制は西欧の「旧体制」と本質的には同じ体質を持っていたために、ロシアの西欧政治への登場は西欧の列強によって決して違和感をもって迎えられることはなく、むしろ西欧の市民革命にイデオローグたちは、自国の「旧体制」よりもロシアの「専制体制」に、自分たちの理想の実現の望みを託していたほどなのだ。しかし、1789年、フランス革命が起こり、西欧に市民社会が成立するようになると、社会の成立原理の違いの故に、ロシアは次第に西欧にとって異質な存在と見なされるようになるのである
だが、その場合にも、ロシアと西欧との対立の図式はすぐに出来上がったものではなく、それ以前に、1815年、ナポレオンの敗北を契機として、エルベ河を挟んだ「西と東」の対立のイメージがまず出来上がった。「リベラルな西」(イギリス、フランス)対「君主国の東」(プロシア、オーストリア、そしてロシア)という関係である。そしてこの関係がやがて、オーストリアとプロシアの君主体制が弱体化し、ロシアが旧体制の盟主として国際政治の舞台に登場するに及び、「西欧対ロシア」の図式が定着することになる。その時ロシアに与えられたイメージは「オリエンタル・デスポチズム」であった。しかし、ニコライ一世後、大改革の時期を経て、ロシアは保守派にしてもリベラルにしても、また社会主義者にしても、西欧にカウンターパートを持つ国として、ヨーロッパの一員となる。「3」にいう「戻ってきたヨーロッパとしてのロシア」とはそのような意味である。
ところで、著者はヨーロッパ大陸を総体としてとらえ、ここに東西文化の勾配曲線(gradation)なるものの存在を認める。これはゲルシェンクローンの図式を援用したものだが、それによるとヨーロッパ大陸を東に行くにつれて工業化が遅れ、農業が優位を占めるようになり、政治経済の活動における国家の役割も増大する。このことが近代化の度合いをも決定する。ロシアはこの勾配曲線の最東端の国である。強固な専制体制と農奴制の存在はこれによって説明される。
では「近代化」の主要なメルクマールとは何か。それはフランス革命のスローガン(「自由」と「平等」)に示されている。しかし、メイリアに言わせれば、「自由」と「平等」とは、そのままでは本来的に両立しない。「自由」の原理だけでも、また「平等」の原理だけでも、社会は成立しない。従って、「自由」の原理を犠牲にして「平等」の原理だけを追求する「社会主義」は、本来的に実現不能な思想であった。(マルクス主義とはつまるところ、そのような思想の一種に過ぎない。)では、両者はどのように両立させうるか。メイリアによれば、普通選挙と立憲政治を主要な内実とする「民主主義」によってである。これは「自由」の原理を基調としつつも民意が反映されるという点で、平等化への志向をも内包する。メイリアにとって「近代化」の度合いはこのようなものとしての「民主主義」の成熟の度合いである。そしてこの程度が東に行くにつれて低くなるというのである。
しかるにこの勾配曲線の東端の国・ロシアに「平等」を標榜する「社会主義革命」が起こる。かくて西欧とロシアの対立は今度は「資本主義」と「社会主義」の対立に置き換えられる。だが、メイリアによれば、そもそも、両者は同じレヴェルの概念ではない。「資本主義」は実態が先にあり、後から名前が与えれたのに対して、「社会主義」はイデオロギーとして存在してきたにすぎないからだ。従って、「社会主義」の建設はイデオロギーによる支配とならざるをえない。マルクス主義流にいえば、上部構造に合わせて下部構造を作るという「アベコベ」の社会、「シュール・リアル」な社会でしかありえない。しかもマルクス主義という工業国用のイデオロギーを農業国ロシアに当てはめられた。この無理がソヴィエトに全体主義の色合いを与えことになる。
だが、西欧は、恐れるにしろ歓迎するにせよ、「平等」や「社会主義」という言葉に幻惑された。それらは近代市民社会、「資本主義」社会の弱点を突くものであり、近代が生み出した最先端の理念と見なされていたからだ。西欧はこの理念がソヴィエトで実現されつつあると考え、それ故にある者はこれに恐怖し、またあるものはこれに期待をかけた。いち早く深刻な問題を嗅ぎつけたものたちは、その裏切りをなじり、それらの理念の実現を別の場(中国やヴェトナムやキューバなど)に求めた。だが、その誰ももが、理念そのものが実現不可能であること、ソヴィエトが足のない「ミラージュ」に過ぎないことに気がつかなかったのである……。
以上、概要を走り書きした。これは勿論本書の骨子に過ぎない、従って、大事な肉がそぎ下ろされ、血も抜き取られている。そのため、メイリアの説は旧来の「全体主義論」とさして変わりのないもののように見えてしまうことを恐れる。著者自身、「全体主義論」の復権を言っているから、このような読まれ方も決して的外れではないのだが、依って立つ思想的基盤は柔軟なリベラリズム、論拠は重層的でかつ豊富、論の進め方は醒めいてかつ緻密、語り口はスパイスの効いたウイットに満ちている。旧説の単なる復活と見なされるべきではないだろう。
わが国の論者の中にはメイリアの『悲劇』を「イデオロギッシュ」と断ずる向きもあったが、私には、メイリアの著作は二つとも、イデオロギー批判の書と読める。もっとも、イデオロギー批判もまた歴史のコンテキストの中では別のイデオロギーとなってしまうものではあるのだが。例えて言えば、メイリアのロシア・ソヴィエト論自体、どのような歴史状況の所産であるのか、という問が当然生まれよう。だが、これは自ずから別問題であろう。
なお、メイリアの学友パイプス(彼らは共にハーバード大学の同期生である。)の『ロシア革命史』が、近く、西山克典氏の邦訳にとって成文社から刊行される。これでカルポーヴィッチ門下生の最新のロシア史論、ロシア革命論が出そろうことになる。これまで「修正主義論」が主流を占めてきたわが国のロシア史学会に話題が提供されることを期待したい。